自宅で育てている観葉植物のモンステラが、ある時から明らかに成長が鈍くなりました。
いつもなら次々と葉が伸びて“ジャングル状態”になるのに、なぜか元気がありません。
思い当たる節は、土の入れ替えをしたことでした。
普段はあまり行かない、植物を大きく扱っているフラワーパークで購入した観葉植物用の培養土に替えたのです。
マンション暮らしなので、普段は土をできるだけ再生して使うようにしていますが、この時は思い切って土を入れ替えました。ところが、それ以降どうも生育が良くありません。
「培養土って、どれも同じじゃないの?」
そんな疑問が湧いてきて、今使っている土をベースにしながら、培養土の種類や用土の違い、選び方について改めて整理してみることにしました。
この記事では、培養土の基本から、失敗しにくい選び方、自作や再利用の考え方まで、初心者向けに分かりやすくまとめています。
培養土とは
培養土とは、複数の用土と肥料をあらかじめ配合し、植物が育ちやすい状態に調整された土のことです。
観葉植物用、野菜用、多肉植物用など、育てる植物の種類や用途に合わせて、水もち・水はけ・通気性・養分バランスが考えられています。
園芸で使われる「用土」は、赤玉土や腐葉土などの単体素材を指すのに対し、
培養土はそれらをブレンドして“すぐ使える状態”にしたもの、と考えると分かりやすいでしょう。
市販の培養土は袋から出してそのまま使える手軽さがメリットですが、
配合されている素材や性質は製品ごとに違うため、「どれでも同じ」というわけではありません。
必要に応じて、自分で用土を配合して作ることも可能です。
植物を超元気にする天然植物活力液「HB-101」。
植物本来の力を最大限に引き出せます。
培養土の種類
培養土にはいくつか代表的なタイプがあり、用途によって向き・不向きがあります。
たとえば、
- 多くの植物に幅広く使える「汎用タイプ」
- 水はけを重視した「粒状培養土」
- 発芽や発根を重視した「種まき・挿し木用培養土」
- 油粕や魚粉などの有機質肥料を含む「有機培養土」
などがあります。
初心者の場合は、まず育てたい植物に合わせた専用培養土を選ぶのが失敗しにくい方法です。
市販品は手軽に使えますが、パッケージの裏面を見て、どんな用土が使われているかを確認するだけでも、失敗のリスクはかなり減らせます。
代表的な用土
培養土は、以下のような「基本用土」と「改良用土」を組み合わせて作られています。
それぞれの特徴を知っておくと、市販の培養土を選ぶときや、自作するときの参考になります。
| 基本用土 (ベースになる用土) | 赤玉土 | 赤味の強い弱酸性の土。 透水性・保水性・肥料もちに優れたバランスの良いタイプで、多くの植物に適しています。粒の大きさや硬さが異なるので、求める保水性などの性能に合わせて粒の大小を選びましょう。 |
| 鹿沼土 | 黄色っぽい火山性の土。栃木県鹿沼地方で採取。 通気性や保水性に優れている点は赤玉土と同様ですが、酸性が強い土質で酸性を好む、サツキやツツジなどの栽培に使用されます。 | |
| 黒土 | 黒っぽく、フカフカとした感触で、根菜などの野菜の栽培に適した土です。有機質を多く含んでおり比重が重く、肥料もちや保水性に優れています。 | |
| 日向土 | 茶色~黒色の軽石のような土。宮崎県南部で採取。 軽くて硬いので通気性・水はけに優れており、改良用土としても使用されます。湿ったものは「ボラ土」と、呼び名が変わります。 | |
| 軽石 | 火山から採取される白い石。多孔質のため軽くて通気性が非常に良く、水はけに優れています。通気性を好むランなどの栽培の他、鉢の底に敷く石としても使用されるものです。 | |
| 水苔 | 湿地の苔を乾燥させた、粘り気のある黒い土。 通気性・保水性に優れており、盆栽の石づけやランの植え込み材などに使用されます。 | |
| 改良用土 (補助する用土) | 腐葉土 | クヌギやケヤキなど広葉樹の葉や枝を発酵させたもの。 通気性・保水性・肥料もちに優れ、有機質も含んでいるため幅広い場面で使用できます。選ぶ際は発酵が完了して黒くなっているもの・葉の形が程よく残っているものがおすすめです。 |
| 堆肥 | 植物由来の有機物を発酵させたタイプと動物由来の有機物を発酵させたタイプがあります。腐葉土と同じような目的で使われますが、堆肥の方がやや肥料分が豊富で、土に養分を与えられることが特徴です。 | |
| 天然砂 | 花崗岩が風化した「山砂」、河川の岩石が風化した「川砂」があります。通気性を良くするといった目的に適したものです。 | |
| パーミキュレート | ヒル石を高温処理したもの。 薄い板が積み重なったような多層状の構造になっています。軽くて保水性・通気性に優れており、土壌改造以外にも種まき用土などに使用されます。 | |
| パーライト | 真珠岩や黒曜石を高温で焼いた、非常に軽い粉状の白い石。 多孔質なので通気性・水はけに優れており、用土の通気性を改善するなどの目的で使われます。 | |
| ピートモス | 苔や柳、アシなどが堆積してできた土です。酸性が強いので、用土を酸性に傾けたい時などに使用します。保水性に優れていますが、一度乾燥させると吸水するまでに時間がかかるため気をつけましょう。 |
植物が元気に育つ土の条件
植物は土の中で根を張り、水分や養分(N=窒素、P=リン酸、K=カリなど)を吸収して成長します。
そのため、どんな土を使うかは、生育に大きく影響します。
特に重要なのは、次のポイントです。
植物の根が丈夫に育つためにはどの様な状態が必要か?
- 保水性が有り、十分な養分を供給出きる。
- 排水性、通気性があり酸素を根に十分に供給する。
- アルカリ性や酸性に偏っていない。
- 堆肥や腐葉土などの有機物が含まれている。
- 清潔な土。害虫や病原菌、雑草の種子、異物など含まない。
培養土を選ぶときは、「この条件を満たしていそうか?」という視点で見ると、失敗しにくくなります。
プロも愛用の人気植物活力液!全ての植物にオススメ。≪送料無料≫植物を超元気にする天然植物活力液「HB-101」。
植物本来の力を最大限に引き出せます。
培養土を自作する
培養土は、基本用土と改良用土を組み合わせ、肥料の量や配合比率を調整すれば、自分で作ることもできます。
この配合の違いによって、植物に合う・合わないがはっきり分かれます。
ホームセンターで売られている培養土は、メーカーごとに配合が調整されており、それぞれに特徴があります。
慣れてくると、栽培目的に合わせて自分でブレンドするのも楽しくなってきます。
ただし、初心者がいきなり自作する場合に特に注意したいのが酸度(pH)の調整です。
これが合っていないと、肥料や水をきちんと与えていても、植物がうまく育たない原因になります。
多くの観葉植物は、中性〜弱酸性(pH6.0〜7.0)を好むものが多いとされています。
また、市販の培養土は殺菌処理されていることが多いため、自作する場合は病害虫対策にも注意が必要です。
植物を超元気にする天然植物活力液「HB-101」。
植物本来の力を最大限に引き出せます。
培養土の再利用
自宅で植物を育てていると、植え替えのたびに古い土が出ます。
特にマンション暮らしでは、土の処分に困ることも多く、できれば再利用したいと考える人も多いでしょう。
ただし、使い古した培養土には、古い根やゴミが混ざっているだけでなく、害虫や病原菌が潜んでいる可能性もあります。
再利用する場合は、まずふるいにかけてゴミや古い根を取り除きます。
その後、ビニール袋などに入れて直射日光に当て、熱消毒を行う方法があります。目安としては、60℃以上の状態で40分以上加熱できると、病害虫や雑草の種子を減らせるとされています。
消毒後は、肥料や腐葉土などを適量追加し、再び植物が育ちやすい状態に整えてから使うようにしましょう。
プロも愛用の人気植物活力液!全ての植物にオススメ。≪送料無料≫植物を超元気にする天然植物活力液「HB-101」。
植物本来の力を最大限に引き出せます。
まとめ
植物を元気に育てるためには、水やりだけでなく、土選びもとても重要です。
市販の培養土は手軽で便利ですが、「どれも同じ」ではなく、植物や用途によって向き・不向きがあります。
用土の特徴を少し知っておくだけでも、培養土選びや土の再利用で失敗しにくくなります。
まずは専用の培養土を上手に使い、慣れてきたらブレンドや再利用にも挑戦してみると、園芸がもっと楽しくなるはずです。
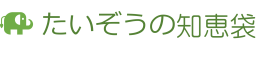
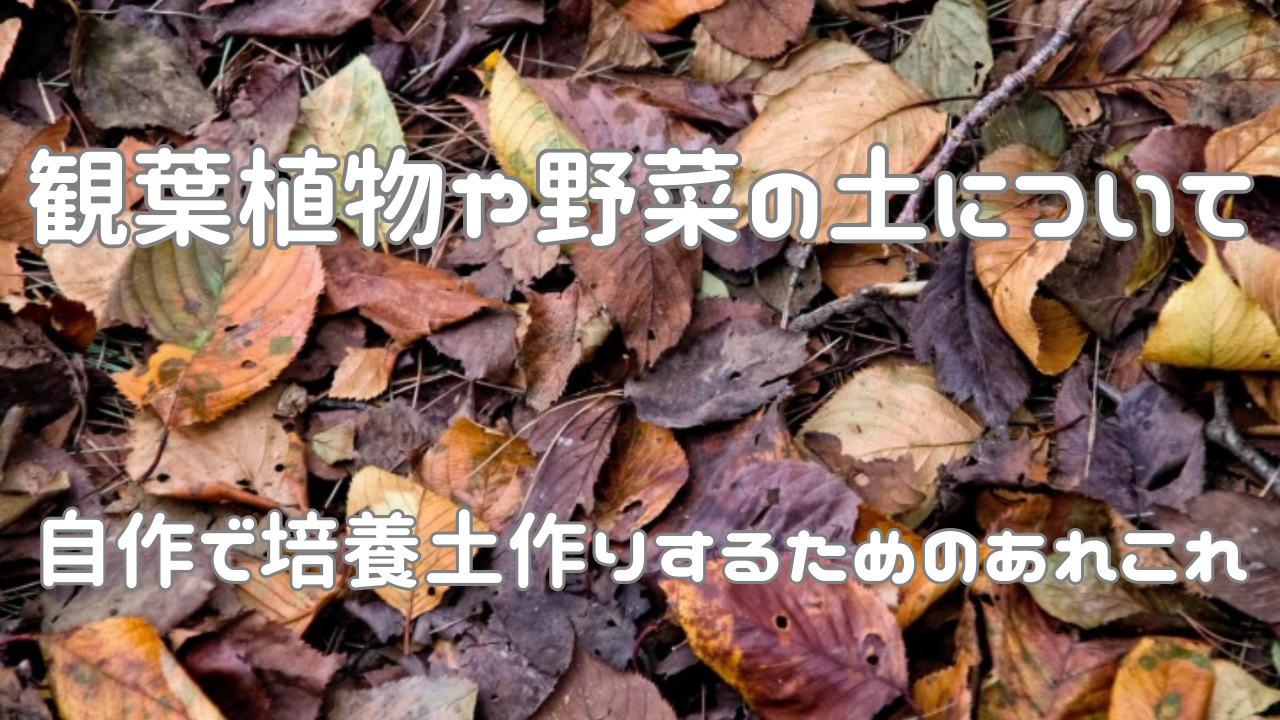

コメント