【話題曲分析】クロダサギ「異邦人」替え歌がSNSで拡散中|風刺とユーモアの境界線
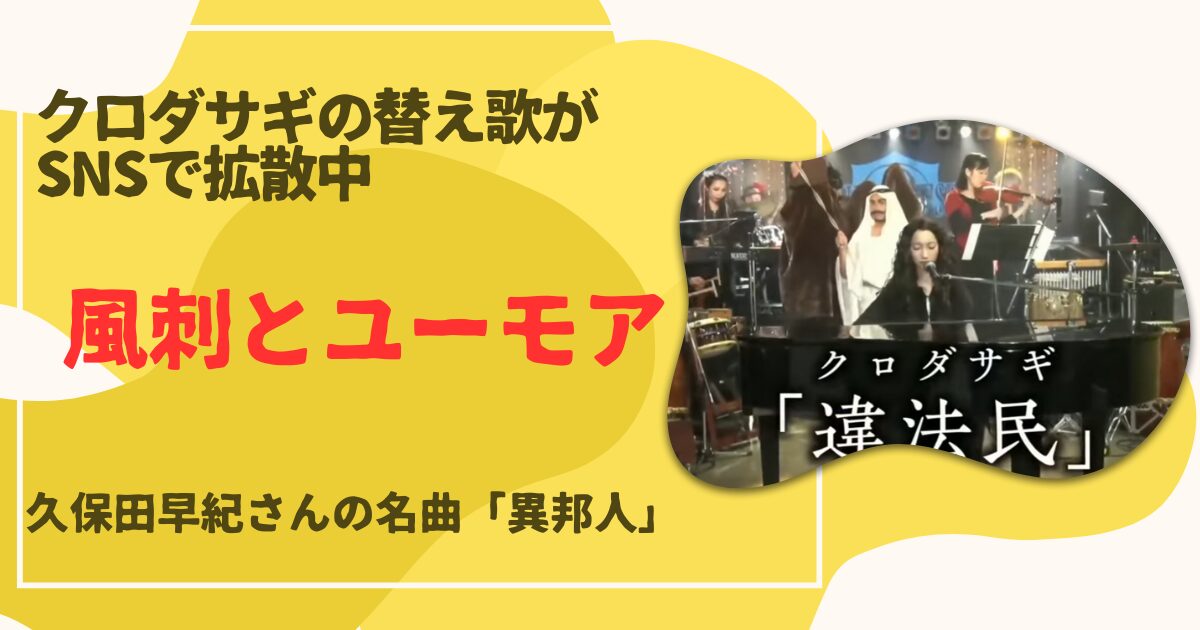
久保田早紀さんの名曲「異邦人」が、令和の時代に新たな形で注目を集めています。
SNSでクロダサギさんが謳う、久保田早紀「異邦人」の替え歌が130万再生を突破。
風刺とユーモアが交錯する“現代の風刺ソング”として注目を集めています。
目次
懐かしの名曲が、風刺ソングとして再び脚光を浴びる
1979年にリリースされた久保田早紀さんの「異邦人」は、オリエンタルな旋律と詩的な世界観で一世を風靡しました。
その名曲をもとに作られた替え歌は、現代社会のある側面を風刺した内容となっており、ユーモアと皮肉が絶妙に織り交ぜられています。
視聴者のからは。
「地上波に出演して欲しいくらい素晴らしいです!」「よく言ってくれた」「歌詞のセンスが鋭い」と共感を示す声が。
よかったらシェアしてね!
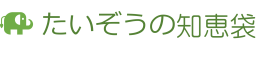
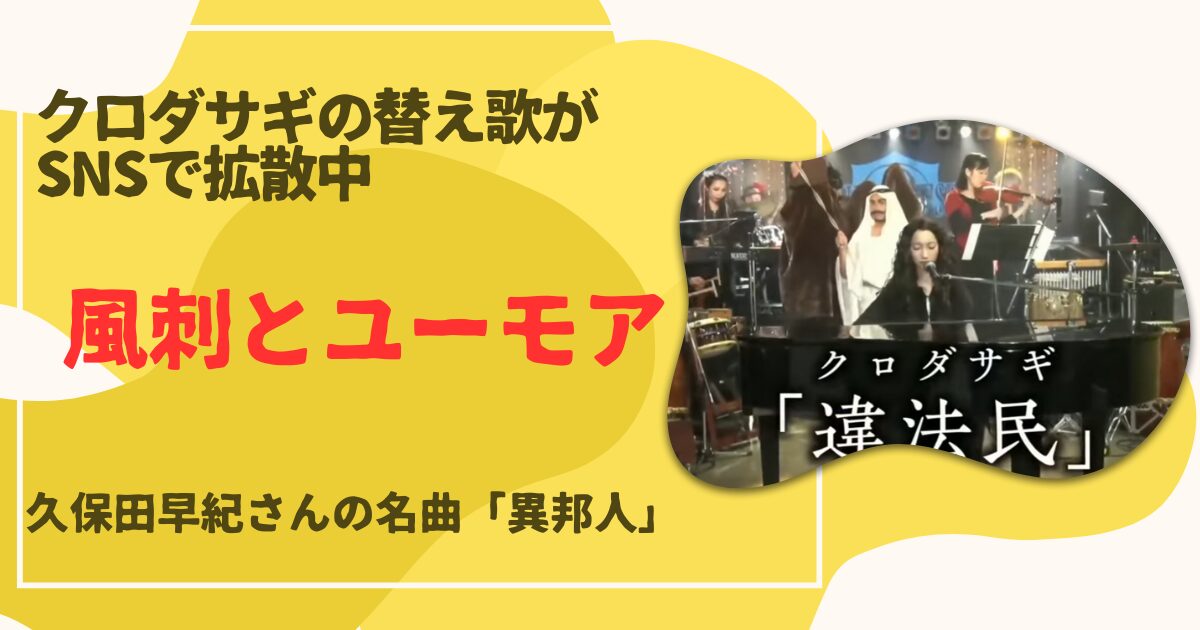
コメント