秋になると街がオレンジや黒の装飾で彩られ、「ハロウィン」の話題が増えてきますね。
ハロウィン(ハローウィンとも呼ばれます)は、毎年10月31日に行われるお祭りです。
渋谷などでは仮装した若者たちが集まる様子がニュースになりますが、
そもそもハロウィンとは、いつ・どんな意味を持つ行事なのでしょうか?
この記事では、ハロウィンの起源・由来・仮装の理由・かぼちゃの意味まで、
知っているようで意外と知らないハロウィンの基礎知識をわかりやすく解説します。
ハロウィンとはどんなお祭り?
ハロウィン(Halloween)は、アメリカを中心に世界各国で親しまれているお祭りです。
日本でも秋の恒例行事として定着し、仮装やコスプレを楽しむイベントとして知られるようになりました。
もともとハロウィンは、ヨーロッパ発祥のお祭りで、11月1日キリスト教の諸聖人に祈りを捧げる祝日「諸聖人の日」「万聖節」(All Hallo)の前夜祭(All Hallo Eve)と言う意味で10月31日に行われるお祭りのことです。
「All Hallows’ Eve(オール・ハローズ・イヴ)」が短縮されて「Halloween」と呼ばれるようになりました。
All Hallow’s evening → Hallow’s even → Hallowe’en
ハロウィンは、古代ケルト人の収穫祭と先祖供養の儀式に由来します。
現在は秋の収穫を祝い先祖の霊をお迎えするとともに悪霊を追い払うお祭りで、古代ケルト人が行っていたお祭りに由来しています。
ジャガイモ飢饉でアメリカ合衆国に渡ったアイルランド系移民によりアメリカに定着し、今では日本も含めて世界各地で祝われるお祭りになりました。
ハロウィンの起源と歴史
もう少し詳しくハロウィンの起源について。
ハロウィンは2000年以上前の古代ケルトのドゥルイド教で行われていたサウィン祭(Samhain)が起源と言われています。
古代ケルトの暦では、11月1日が新年でした。大晦日にあたる10月31日の夜に祖先の霊が戻ってくると信じられていました。
しかし、悪霊も一緒にやって来てしまい作物に悪い影響を与えたり、現世の人間たちに悪さをすると言われていました。
そこで、悪霊を追い払うために火を焚き、仮面をかぶって身を守ったのです。
ケルト人の自然崇拝(自然及び自然現象に神秘的力や存在を認め、これを崇拝すること。太陽崇拝・樹木崇拝など)の文化がキリスト教へ吸収されていく過程で、10月31日のケルトの祭りの風習は残り続け「諸聖人の日」が出来たと言われています。
この風習がキリスト教文化と融合し、やがて「諸聖人の日」の前夜祭=ハロウィンとなりました。
当初は宗教的な意味を持っていましたが、現在では宗教色のないイベントとして楽しまれています。宗教行事としてハロウィンは行われていません。キリスト教会ではハロウィンの習俗の解釈や賛否が分かれています。
移民とともにアメリカに伝わったハロウィンは、子どもたちには大変に怖い内容だったことから19世紀の後半頃から子どもたちでも楽しめるイベントに変化していったとのことです。
ハロウィンでなんで仮装するのか?
古代ケルト人は、悪霊に取り憑かれないように自らも魔物の姿に変装したとされています。
つまり「仲間のふりをして襲われないようにする」ための仮装です。
古代ケルトでは10月31日は死後の世界との扉が開き、ご先祖様の霊が家族に会いに現世に戻ってくる日と考えられていました。日本のお盆と同じ考えです。
しかし祖先の霊と一緒に悪霊や魔女もやってきて、現世の人間たちに災いをもたらしたり、いたずらをするため、現世の人々は身を守るため悪霊や魔女の格好をして仲間に見せかけるため仮面をつけたり仮装をしたのが始まりです。悪霊たちがその格好を見て驚いて逃げるという説もあるようです。

この仮装はアメリカでは「恐ろしい」と思われているものが選ばれ、幽霊・悪魔・黒猫・ゾンビや吸血鬼、狼男、フランケンシュタインなど欧米の恐怖小説に登場する怪物なども含まれるようです。
20世紀後半ごろからのアメリカでは海賊のキャラクターやスパイダーマン、バットマンなど漫画や映画などのキャラクターにも仮装されるようです。
仮装以外にも魔除けの焚き火を焚いたりしたと言われています。
ジャック・オー・ランタン(かぼちゃの意味)
ハロウィンといえば、目と口をくり抜いたカボチャのランタン。
これは「ジャック・オー・ランタン(Jack-o’-Lantern)」と呼ばれています。

ジャックとはアイルランドの民話よると悪魔をだました男の名前で、生前に悪いことばかりしていたジャックは、魂を取ろうとやって来た悪魔を騙し魂を取らないように約束させましたが、生前の悪行から天国へはいけず、地獄に落ちることも出来ず、カブをくり抜いて作ったランタンに灯をともし死後も闇夜をさまよい続けたというお話があり、そこからの由来のようです。
最初はカブだったようですが、アメリカに伝わってからカボチャに変わったようです。アメリカではカブは馴染みが無くカボチャの方が手に入りやすかったからだと言われています。
スコットランドなどの一部の地域では現在もカブをくり抜いたものでランタンにしているそうです。
怖い顔にくり抜いて内側に火のついたローソクを立て、ハロウィンの晩、家の戸口の上り段に置いて魔除けの効果になり、悪霊を怖がらせて追い払うことが出来ると言われています。
「トリック・オア・トリート!」の意味

トリック・オア・トリート!(Trick or Treat!) = お菓子をくれなきゃいたずらするぞ!!
これは省略文です。
判りやすくすると「Treat me,or we’ll tick you」日本語にすると「もてなせ、さもなくば悪事を働くぞ」となるようです。
本場アメリカでは、ハロウィンといえば仮装をした子どもたちが街を練り歩き、この言葉を玄関先で声をかけてお菓子をねだります。
子どもたちに「トリック・オア・トリート!」言われた大人たちは「ハッピーハロウィン」と答えてお菓子を渡す習わしが有ります。
「トリック・オア・トリート」は1920年代にこの言葉が登場し、徐々にアメリカ全土へ広まりました。
ハロウィンの風習として定着したのは1950年代になってからのようです。
その頃には映画のタイトルになったり募金活動の名称に採用されるなどして、見知らぬ子供の訪問を怪しむ人はいなくなったのだそうです。
徐々に浸透し楽しく仮装してお菓子をもらうイベントとして、アメリカを中心として子供たちに広まりました。
これは魔除けの意味が込められていて、悪霊にお菓子を渡し家に入ってこないようお願いして、悪霊を追い払うなどの意味があるそうです。日本の節分に似ていますね。
しかし、日本では「トリック・オア・トリート」は根付いてはいないものの、仮装パレードは全国各地に広まりコスプレは本場アメリカをも凌ぐクオリティを見せているようです。
日本では年中行事の一つで、非日常を味わうイベントとして浸透しているようですね。
日本ではいつから流行り出しの?
日本で最初にハロウィンを取り扱ったのは1970年代の原宿にあった「キディランド原宿店」だと言われているそうです。
販促活動の一環でハロウィンの仮装パレードが始まりとのことです。その後、1990年代から2000年代にかけて商業イベント化し他社も着目し徐々に広まって行きました。
日本の高度成長に合わせ1970年代はアメリカ文化が押し寄せて来る中で浸透していったのだと思います。
日本の1980年代はバブル期を迎え東京ディズニーランドも開園し1997年にディズニー・ハロウィンイベントが開催されるようになり現在は秋の恒例イベントに成長しています。
まとめ
由来や起源を知ると、日本の大晦日やお盆、収穫祭などが混ざりあったようなイベントですね。
日本でのハロウィンは、どちらかというと「楽しむ」イベントとして発展していますが、
本来の意味を知ることで、また違った視点から楽しめそうですね。
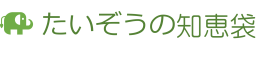



コメント