なぜか私たちは電話をかけるとき、当たり前のように「もしもし」と言いますよね。
なんで?
この様な質問をされて答えられますか!
日常会話で「もしもし」とはあまり使いませんよね。
なぜ電話の時に第一声に特別にこの言葉を使うのでしょうか?
最近は、web会議などリモートで打ち合わせをすることが身近になっていますが、顔画像は映さず資料だけ映している場合も呼びかけに「もしもし」と使っていませんか?
この記事では、その語源や歴史、他国との違いを分かりやすく解説します。
「もしもし」の語源とは?
電話で最初に発する「もしもし」という言葉。
実は、これは 「申す申す」 から生まれた表現です。
日本語の「申す(もうす)」は、へりくだって「言う」という意味を持ちます。
つまり「申す申す」とは、「私が話していますよ」「声が届いていますか?」という、相手を気遣った呼びかけだったのです。
その後、発音がやわらかくなり、言いやすい「もしもし」と変化していきました。
明治時代に広まった「もしもし」
日本では電話機が登場したのは明治時代になります。その時代にさかのぼり紐解いていきます。
電話の黎明期
日本で電話が一般に使われ始めたのは明治23年(1890年)ごろのことです。
当時の人々は、電話をかけた相手に声が届いているか確認するため、最初に「おい!」「こら!」と呼びかけていたそうです。
しかし、これでは相手に対して失礼であると考えた郵便電信局が「申す申す」と言うよう指導しました。これが、やがて一般の利用者にも広まり、電話での標準的な挨拶になったのです。
なぜ普及したのでしょうか?
・発音しやすく、耳に届きやすい
・「申す」という言葉に丁寧さがある
・相手の存在を確認できる便利なフレーズ
こうした理由から「申す申す」が浸透していき、自然の流れで言いやすい「もしもし」に変化していき全国で使われるようになりました。
他の国の電話の挨拶
日本では「もしもし」が定着しましたが、国によって電話の最初の言葉は異なります。
英語圏 :Hello(ハロー)
フランス語圏:Allô(アロー)
中国語圏 :喂(ウェイ)
韓国語 :여보세요(ヨボセヨ)
これらはいずれも「聞こえていますか?」「今、通話がつながっていますよ」という確認の意味を持っています。
その中でも日本の「もしもし」は、相手にへりくだる「申す」から来ているため、より丁寧で独特な文化的背景を持っています。
現代での「もしもし」の使い方
現代でも「もしもし」は電話の第一声として使われていますが、いくつか注意点があります。
・ビジネスの場面では控える場合も
会社の代表電話を取る際は「はい、○○株式会社でございます」と名乗るのが基本です。
・親しい間柄では今でも自然に使われる
友人や家族との電話では「もしもし」は今でも活躍しています。
・スマホ時代でも変わらない
LINE通話やスマホアプリの音声通話でも、つい「もしもし」と言ってしまう人は多いのではないでしょうか。
・web会議などリモートでも顔画像は映さず資料だけ映している場合にも呼びかけに「もしもし」と使っていませんか?
音声での通話をする場合は「もしもし」は定番ですね!
まとめ
電話で使う「もしもし」は、
・語源は「申す申す」
・明治時代に郵便電信局の指導で広まった
・世界の挨拶の中でもユニークな「謙譲表現」
という歴史を持った表現です。
普段は何気なく口にしている「もしもし」ですが、そこには “私が話していますよ、声は届いていますか?” という相手を思いやる気持ちが込められているのです。
ちょっとした雑学として覚えておくと、話のネタにもなりますよ。
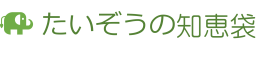
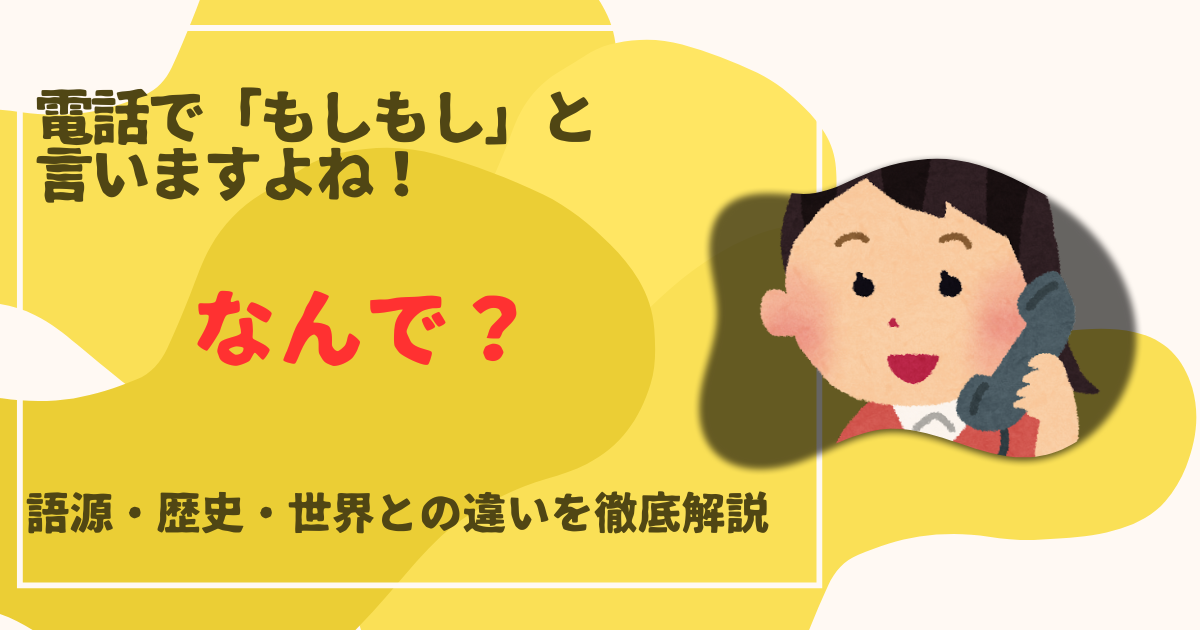
コメント