愛知県豊明市議会は、2025年9月22日、「スマートフォン等の適正使用の推進に関する条例案」を可決しました。施行は10月1日から。
市民に対して「余暇時間におけるスマホの利用は1日2時間を目安に」と呼びかける全国初の条例です。
ニュースでは「スマホ2時間ルール」というフレーズが独り歩きしていますが、ではなぜ豊明市はこうした条例を制定するに至ったのでしょうか?
このニュースから考察してみました。
背景にあるのは“睡眠不足”と“生活リズムの乱れ”
豊明市が着目したのは、市民、とりわけ子どもの睡眠不足でした。
スマートフォンやタブレットの利用時間が長くなると、どうしても就寝時間が遅くなり、翌日の生活リズムに影響します。
教育現場からも「授業中に集中できない」「夜更かしで体調を崩す子が増えている」という声が上がっており、健康や学習への悪影響が課題として浮かび上がっていました。
「スマホ否定」ではなく「使い方を考えるきっかけ」
条例の目的は、スマホやゲームを頭ごなしに否定することではありません。
市の公式説明でも「ゲームやSNSを否定するのではなく、健やかな生活を送るための啓発」と明記されています。
つまり、「スマホを使うな」ではなく、「どのくらいがちょうど良いのか、意識してほしい」という呼びかけ。
2時間という数字はあくまで“目安”であり、守らなければ罰則があるわけではありません。
コロナ禍以降の利用急増も後押し
もうひとつの背景には、コロナ禍があります。
リモート授業や在宅ワークが広がり、スマホやタブレットは生活に欠かせないツールとなりました。
その一方で、娯楽としての長時間利用が加速し、「依存傾向」が全国的に問題視されるようになりました。
豊明市はこうした現状を踏まえ、「今こそ市民に考えてもらう必要がある」と判断し、条例化に踏み切ったのです。
自由と健康のバランスをどう取るか
もちろん、「余暇時間まで行政が口を出すべきか」という疑問の声もあります。
そのため、議会では附帯決議として以下のようなポイントも付け加えられました。
- 市民の自由や多様性の尊重
- 誤解を招かない丁寧な説明
- 子どもや保護者との協力・支援
- 市民意見を反映させる仕組み
- 効果検証と見直し
強制ではなく、あくまで「市民の健康を守るための提案」として位置づけられているのが特徴です。
豊明市の試みは全国に広がるか
今回のスマホ条例は、全国でも初めて「市民全体」を対象にした試みです。
市民の健康意識を高めるきっかけとして評価する声がある一方、「どこまで行政が生活に介入すべきか」という議論も避けられません。
豊明市のこの一歩が、他の自治体に広がっていくのか。
“スマホ2時間ルール”をめぐる議論は、今後さらに注目を集めそうです。
あなたはどう思う?
「スマホの使用時間を1日2時間に抑える」という提案。
健康や睡眠のために有効だと思いますか?
それとも「個人の自由を侵しすぎ」だと感じますか?
ぜひ、自分自身や家族のスマホ利用を振り返るきっかけにしてみてください。
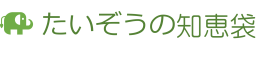

コメント